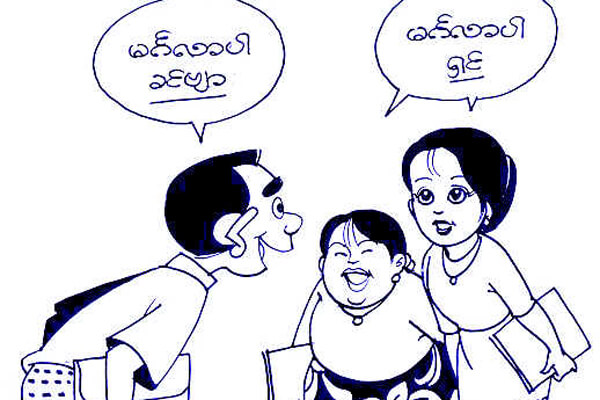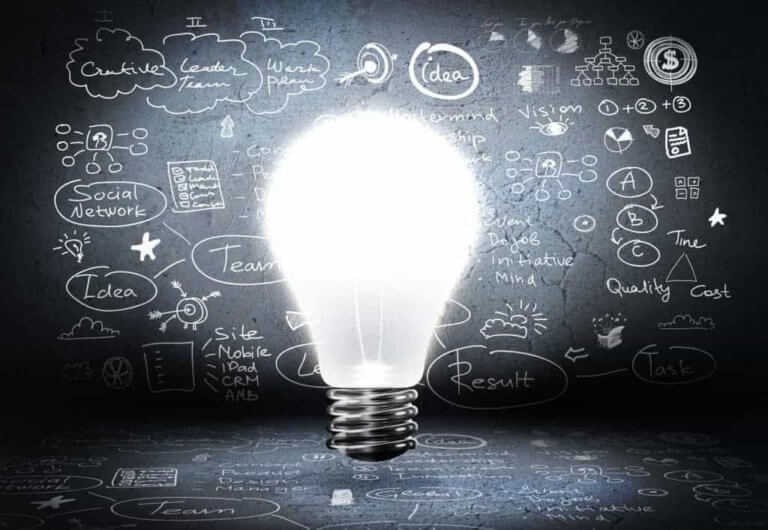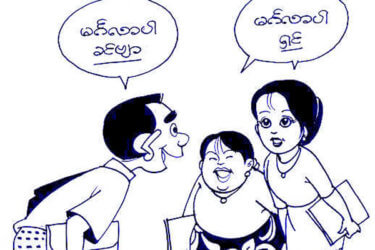ミャンマー語の勉強を始めて二年以上が経過した。
コロナでミャンマーへ行けないのを逆手に取り、今度ミャンマーへ行くときまでに簡単な会話程度はできるようにしたいと思ったからだ。
しかし、ミャンマー語習得へのモチベーション低下が最近著しい。
昨年は現地のミャンマー語教室のオンライン講座を受講していたのだが、今はそれもやっていない。
しかし、細々とだが独学で何とか継続している。
何事も同じだが、新しいものを習得する際には理論と実践の両面を学んでいくのが効率的である。
これら2つのバランスが大切なのだ。
カイロプラクティックも同様である。
知識(理論)だけでもだめだし、技術(実践)だけでもそれを活かすことは難しい。
さらに、理論と技術を関連付けるという作業も重要である。
これら2つが孤立していたら、治療には全く役に立たない知識と技術になってしまう。
言語の習得でも全く同じことが言える。
ぼくが今独学でやっているのは、理論の部分のみである。
まるで中高生の時にやっていた英語の勉強と同じだ(テストではよい点数が取れるかもしれないが・・(笑))。
これでは、面白さも半減である。
半減どころか、非常に「つまらない」状態となっている。
心が「つまらない」と感じているときの反応はただ一つだ。
爆睡である。
おそらく、心の拒絶反応のようなものなのだろう。
そう、ミャンマー語の勉強を始めるとものの数分で爆睡してしまっている。
その傾向は最近特に顕著になっており、ミャンマー語の勉強をやろうと思ったとき(開始前)、すでに睡魔にやられてしまっていることもある。
この現状を打破する唯一の方法は、実践を取り入れることに尽きるだろう。
名古屋にミャンマー人コミュニティがあれば、そういうところにコンタクト取ればよいのだろうが果たしてあるのだろうか(東京の高田馬場にはヤンゴンタウンがあるようだが・・・)。
やはり、ミャンマーへ定期的に行くのが、最適解なのかもしれない。